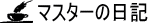
こんにちは。ほろにが従業員のMASTERです。大人気商品のグアテマラ・サンタカタりーナ農園ですが、深煎りに加えて中深煎りを販売開始いたしました。
中煎りも今月の13日あたりから販売予定です。予定外なのですが販売です。理由は簡単。予想以上の美味しさだったからです!是非是非お試しください。もちろん、ご来店のお客様は試飲無料です。
2006年のグアテマラの写真をアップ致します。開業5年目で貯金を叩いて初めてコーヒー生産地に行った思い出深い視察です。

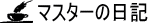
こんにちは。ほろにが従業員のMASTERです。最近ご質問をよく頂いたものの中から、これはもしかしたらお伝えした方が良いのかもと思うものを書いてみます。
「大手のコーヒー豆やさんが25%も値上げをすると聞きましたが、ほろにがでも近いうちに値上げをするの??」
結論から申しますと「今のところ一般小売の値上げの予定はございません」です。確かに需給の問題だったり、ブラジルの干ばつだったり中米のさび病など問題もございます。
今回の問題は為替によるコストアップです。結構な所まで行きましたからね。はぁ、どこまで円は安くなるのでしょうかね。。困りました。
今後、生産国では毎年健全なインフレが起きていくことが予想されます。物価もあがり賃金も肥料も少しずつ上がる傾向にあります。今後のコーヒーの生豆相場は高値安定になり、円高でさらなる仕入コストアップになるかと思います。
今のところは、値上げの予定はございません。が、良い生豆を作ってもらって、良い商品を提供することを重要視してますので、結果、良い生豆を作って貰うために値上げをお願いする時も来るとは思います。
ただ、HPやチラシやら告知などを考えると非常に面倒なので、出来るだけ値上げをしないで耐えようと思います(笑)消費税も上がってほしくないですね。手続きがほんと面倒です。
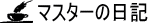
こんにちは。ほろにが従業員のMASTERです。最近ご質問をよく頂いたものの中から、これはもしかしたらお伝えした方が良いのかもと思うものを書いてみます。(前に書いたかどうかも忘れてしまいましたが・・・)
コーヒーの豆の保存方法は何が良いのか?これは、飲むペースや粉OR豆や気温によっても異なるのですが、「冷凍庫で保存」しておけば大失敗は無いと思います。ベターな保存方法だと考えております。特に粉で買われた方や、夏の暑さの中で長時間放置されるよりも冷凍保存のほうが良い結果がでます。
じゃぁ、すべてが冷凍庫の保存が良いのか?と言いますとそのような事はないのですがね。ただ、あまり細かく言えばきりがないですし、そんなに病的なまでに神経質にならなくても良いのかなとも思っています。。。
じゃぁ、冷凍庫に入れない方が良い場合は。
豆の保存場所が17℃以下で湿度、直射日光の当たらない場所であり、焙煎をしてから飲み終わるまでに3日~3週間程度で消費するのであれば常温でokだと思います。
豆にストレスをかけずに、かつきちんと水分が抜けているコーヒーの豆は、きちんと空気を抜いて保存をすれば香味劣化のスピードを抑えられます。逆に良くない焙煎の場合は3日目で明らかに味わいが落ちます。特に味に濁りが強くなります。
焙煎時間が5分程度の短時間で焙煎した豆は、冷凍保存の方が無難な気がしてます。
焙煎豆がどのように煎られたのかで美味しく飲める期間が変わってきてしまいます。ただ、どんな豆でも湿度の低い所で空気を抜いて保存してあればカビの生えることは無いと思います。あくまでも美味しく飲んで頂ける期限です。
コーヒーの豆は10℃保存温度が上がれば2倍の速度で劣化するそうです。その他にも、17℃の温度でコーヒーのオイル分が個体から液体になり1週間程度でコーヒーの香りとオイル分が融合してアロマオイルとなる。と、とある筋からお聞きしました。
鮮度の良い物をお送りするのが大切なのですが、焙煎をして1週間のころが一番こなれた味で美味しいです。とはこの現象と思っております。粉の場合は残念ながら熟成するような感じはあまり経験したことがありません。
ドリップバッグを作るときも豆が落ち着くまで置いて、そのあとミルにかけて作成しますので少々時間がかかってしまいます。焙煎した当日コナにして作成するよりも香りの質も量も味わいも良くなります。コナにしたら早めに飲み切るのがお勧めです。
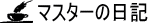
こんにちは。ほろにが従業員のMASTERです。お待たせいたしました!13-14ニュークロプのグアテマラ・サンタカタリーナ農園が入荷致しました!
まずは、深煎りからご紹介しようと準備を進めております!カッピングの段階では最高のクオリティーでしたので、豆の良さを最大限に引き出せるように頑張って焙煎しようと思います!
そんな訳でして、まずはサンタカタリーナ農園の写真集です。お楽しみにお待ちください!
銃を持った門番さんに門を開けてもらってほどなく進むと農園主のペドロ氏の住居とウエットミルが見えてきます。
コンクリートのうえでじっくりと撹拌されながら天日乾燥されます。生豆が蒸れないように、何度も何度も撹拌して蒸れを無くし均一に乾燥させます。
果肉をむく機会です。パルパーと呼ばれます。ドラムが回転して熟した豆のみ皮がむける仕組みです。
農園内はジープで紹介してもらいました。奥に見える建物は教会ですね。
パティオから見えるのがフエゴ火山です。小噴火が毎日あり、機関車のようにモクモク煙を吐いてます。
シェールドツリーと呼ばれる日蔭を作る木の下で、品種別に苗木が育てられています。
コーヒーチェリーは、皮と果肉を剥いてこの水路を使って発酵槽と呼ばれる煉瓦でできた水槽に運ばれます。
この苗木は接ぎ木をした苗木です。様々な品種をどこに植えるのが適切かを考え、生育しています。
食べられるの?とよくご質問をうけますが、好んで大量に食べるものではございません。糖度はありますが青臭い匂いがあり、サクランボやラズベリー、ブルーベリーのような美味しさはありません。ただ見た目が美しく、口に入れると甘いので必ず試食はします(笑)
悪天候の場合に備えて、ボイラーでの乾燥機も完備しております。が、アンティグアのコーヒーは天日干しの風景がよく合います。
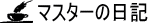
こんにちは。本日からケニアが13-14クロップのティリク・ファクトリーになりました!エリアは二エリ地区になります。大好きなガトンボヤ・ファクトリーと同じエリアになります。
今回の写真はウエットミルの工程をご紹介致します。皮を剥いて、果肉を綺麗に除き水洗いをして天日で乾かします。この工程をウエットミルと言います。
乾かした外皮付きの種(パーチメント)は、乾燥させて脱殻。その後、大きさ、重さ、比重、色彩選別などを経て一つ一つロット番号で管理されます。この工程をドライミルと呼ばれます。
その一つ一つの工程が大切であり、どこかで手を抜くと素晴らしい香味は生まれません。コーヒーは飲んでみないと分からないのでコツコツと自分の味覚を信じて良い素材を探し、出会えたことに感謝し素材の良さを最大限に引き出すように日々頑張っております。
ウエットミルの全貌です。皮や果肉を剥く作業での豆の移動は、水路を使って移送させることが多いです。その為、豊富な水の確保や水質の汚染しないような配慮も大切になります。
ティリクファクトリーのチェアマン。
チェリーが収穫されてましたら、このパルピングマシーンで果肉を剥きます。
果肉を剥くパルピング
画面上部のお風呂のようなものが、ファメンテーション(発酵槽)です。コーヒーチェリーの皮を剥いて果肉を水洗いする場所です。数時間~数日で果肉は綺麗に種(豆)から分離します。
発酵槽の正面です。この発酵槽での処理の良し悪しで香味が変わるようです。
ケニアの場合は、発酵槽に浸けられた後に更に水洗いで綺麗に洗うファクトリーが多いようです。(高級品に限りますが)
こちらは、生豆を綺麗に洗った後にの乾燥場になります。ケニアの高級品はこのように棚の上に干されて天日で乾燥されます。
こちらは、種を取り出したあとの果肉になります。多くの農園では、この廃棄物を発酵させて肥料として再利用してます。